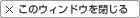![]()
| 出生 | 出会い | 移植実験 | 安息 | ふたたび | カスタムグローブ | 脱走者 | 男の話 | 叛意 | 開幕 |
◎出生◎
K’を超える強化人間の開発を目的として、秘密結社ネスツが生み出したK’の遺伝子(タイプK’ゲノム)を持つ9999番目の実験体。コードネームはЖ´。「K’チルドレン」と呼ばれる同様の実験体は数百体を数えたが、そのいずれもが失敗作であり、最後まで生き残ったのは彼ただひとりだった。
また、この計画は、ネスツが大々的に推し進めていた『プロジェクトK』の副産物的なポジションにあり、組織内では『プロジェクトЖ(ジェー)』と呼ばれていた。※「Ж(ジェー)」はKを背中合わせにした物を示す。
◎出会い◎
ダイモス内の無菌ラボで生み出されたネームレス(コードネームЖ´)は、ほかの実験体たちとともに過酷な日々を送っていた。毎日のように繰り返される改造、調整、そして実験の中で、“兄弟”たちは次々に命を落としていく。彼らにネスツに対する忠誠心などなく、あるのはただネスツへの畏怖と、この情況から抜け出すことはできないという絶望感だけだった。
次に死ぬのは自分なのではないかという恐怖と苛立ちにさいなまれ、次第に生きることに対して投げやりになっていくネームレス。そんなある日、戦闘データを採取するための模擬戦で負傷したネームレスは、ダイモスの救護班ではたらくひとりの少女と出会った。
極秘プロジェクトの産物であるネームレスにはつねに何らかの形で監視がついており、ラボの人間以外と直接会話することを禁じられていたため、少女と話すことはできなかったが、透き通るようにはかなげな、イゾルデという名のその少女との出会いによって、ネームレスは初めて、自分の胸のうちに希望がきざしてくるのを感じた。
これまではいつ死んでもかまわない、むしろ死んでしまえばどんなに楽かとさえ思っていたのに、イゾルデとの出会いはそんなネームレスの生死感を180度変えてしまった。生きてさえいれば、また彼女と会うことができるかもしれない――その一念だけで、ネームレスは過酷な日々に耐え抜いたのである。
しかし、この時のネームレスはまだ、これがネスツによって仕組まれた出会いだったということを知らなかった。
◎移植実験◎
実験体たちの数が当初の10分の1にまで減った頃、プロジェクトは次の段階に移行した。すなわち、タイプK’ゲノムを持つ彼らに、“草薙の炎”を生み出すための因子として、京の遺伝子(プロトKゲノム)を移植する実験が始まったのである。
結果的に『プロジェクトK』の唯一の成功例といえるK’でさえ、“草薙の炎”を完全に再現することはできなかった。『プロジェクトЖ』が目指していたのは、さまざまな強化手術をほどこされたK’と同レベルの肉体で、草薙京の炎を使用させることだった。
だが、プロトKゲノムを移植された実験体たちは、“草薙の炎”に対する拒否反応を起こしたためか、制御不能におちいったみずからの炎に焼き尽くされ、ことごとく死んでいった。ただひとりネームレスだけが、強靭な意志の力で炎の暴走を抑えることに成功したが、それもかろうじて焼け死なずにすんだというだけのことで、とても炎をコントロールして闘えるというようなレベルではなかった。
◎安息◎
結局、ネームレスひとりを残してすべてのK’チルドレンは死亡。これによって『プロジェクトЖ』は失敗に終わり、いずれネームレスも処分されてすべてに幕が降ろされると思われた。
だが、なぜかネスツ上層部はプロジェクト継続を決定し、全身にひどい火傷を負ったネームレスも、右腕を凍結封印された上で集中治療室へと送られた。その看護をまかされたのは、かつてネームレスが出会った、あの新雪のような髪を持つ少女だった。
再会を果たしたからといって、ふたりの間で何かが劇的に変わったわけではない。相変わらずネームレスには監視がついていたし、もともと口数の多いたちではなかったため、自分の世話をしてくれる少女と話し込むようなことはなかった。だが、それでもネームレスにとっては、過酷な実験や苦痛とは縁遠いおだやかな日々をイゾルデのそばですごすことが、なによりのしあわせに思えた。
端的にいえば、ネームレスはイゾルデに恋をしていた。そしてネームレスは、イゾルデもまた自分を憎からず思っていてくれると、うぬぼれではなくそう確信していた。
◎ふたたび◎
火傷が癒え、自力で動くことが可能になったネームレスは、ふたたびラボに戻らなくてはならなかった。一度手に入れた安息の日々を手放すことは、ネームレスにとっては身を切られるよりつらいことだった。病室をあとにする時、自分を見送ってくれたイゾルデの哀しげな表情は、今もネームレスの脳裏に焼きついている。
そんな彼の胸のうちを見透かしたように、ラボの人間はネームレスに告げた。
プロジェクトはまだ進行中であり、現在、草薙の炎を制御するためのネームレス専用のカスタムグローブが開発中である。もしこのグローブを使いこなし、組織に大きく貢献することができれば、組織はネームレスを実験体としてではなく、下級幹部のひとりとして迎える用意がある。下級とはいえ幹部ともなれば、不快な実験や改造、監視などからも完全に解放され、それなりの待遇も保証される。もちろん、基地内を自由に移動することもできるし、もしそれを望むのなら、あの少女を名目上の部下として、つねにそばに置いておくことも許されるだろう――。
それを聞いたネームレスは、進んで過酷な日々に舞い戻ることを決意した。リハビリというにはハードすぎる、弱った肉体をもとに戻すための1日16時間のトレーニング、“草薙の炎”に対する拒否反応を少しでも軽減するための改造手術、そしてデータ採取のための実戦テスト。
しかしネームレスは、ただひたすらにイゾルデとすごす日々だけを夢見てそれに耐えた。
◎カスタムグローブ◎
ネームレスの肉体が、移植実験前をしのぐレベルで完成しつつあった頃、かねてより開発中だったカスタムグローブが彼のもとへ届けられる。青白い輝きを放つそのグローブは、ある種の擬似生命体ともいうべきものであり、装着者であるネームレスの意志を増幅し、暴走状態にある炎をほぼ完璧に押さえ込むことを可能とするものだった。
さっそく凍結封印されていたネームレスの右腕が解凍され、代わりにグローブが装着されたが、移植実験の時の惨劇が繰り返されることはなく、グローブはネームレスの強靭な意志をよく助けて炎を押さえ込むことに成功していた。
これによって、草薙京やK’とは違った形ではあるが、ネームレスもまた強力な炎をみずからの武器として使いこなすことが可能となった。また、擬似生命体であるグローブは、ある程度自由に変形する能力を持っており、これを接近戦用の武器として炎とともに併用するという、ネームレスならではの戦闘スタイルがここに確立した。
身につけた瞬間からまるで自分の身体の一部であるかのようによく馴染むグローブに、ネームレスは歓喜した。このあらたな“腕”さえあれば自分は何でもできる。もう一度あの少女との日々を手に入れるためなら、どんな困難な任務でも遂行できる――。
その思いの強さが、ネームレスをさらに強くしていった。
◎脱走者◎
グローブを使ったテストがすむと、ネームレスは生まれ育ったダイモスを離れ、自然な重力が支配する地球へと送り込まれた。性能実験を兼ねた実戦的な任務に就くためである。破壊工作や要人暗殺といった、非人道的な任務ばかりだったが、少女と触れ合うことによってネームレスの感情に変化が見られた。今まで平然と人を殺してきた彼だが、最近は相手の急所を外すなど、この辺はネスツも誤算だったと言えるだろう。
そんなある日、ネームレスにあらたな任務が下される。ネスツの基地から脱走した科学者の抹殺という、さして珍しくもない任務だったが、ネームレスにとっては自分の評価をさらに高めるチャンスのひとつだった。ネームレスは上層部の期待に見事に応え、いずこかの公的機関と接触する前に脱走者を補足し、追い詰めることに成功した。
その脱走者は、ダイモスのラボでプロジェクトに関わっていた科学者のひとりだった。
男はネームレスに、見逃してもらうのと引き換えに、ネームレスの知らない真実を教えてやると持ちかけてきた。ネームレスの任務はこの男の抹殺であったが、男があの少女に関することだと口にしたため、ネームレスもひと通り話を聞いてみる気になった。
◎男の話◎
男によれば、すべては最初から仕組まれていたのだという。
ネームレスが大怪我を負い、その治療のために送られた治療室であの少女と出会ったことも。
ネームレスがイゾルデに恋をし、それがささえとなって過酷な移植実験に耐え抜いたことも。
ネームレスとイゾルデがたがいに惹かれ合い、別れがたい無二の存在だと思うようになったことも。
そして、真実を知らないネームレスが、イゾルデのためにネスツの忠実な駒となったことも。
――そのすべてが、『プロジェクトЖ』の一環として、最初から仕組まれていたことだったのだと、男は告白した。
ネームレスには、男が何をいっているのかすぐには理解できなかった。
だが、徐々にその意味を理解し、そして、自分がただの道化でしかなかったことを理解した。
要するにネスツは、ネームレスの潜在能力を引き出すために、彼をあのイゾルデと引き合わせたのだった。ふたりが偶然だと思っていた出会いは、本当はネスツによって演出されたものだった。
イゾルデとふたたび会うためにネームレスが限界を超えた耐久力を発揮するであろうことも、彼女をエサにすればどんな任務にも進んでおもむくであろうことも、すべてを見越した上でネスツがやったことだった。現にこうしてネームレスは、上からいわれるままに数々の任務をこなしてきている。
だが、それだけならネームレスも、ここまでの怒りと絶望にさいなまれることはなかっただろう。何よりもネームレスにとって衝撃的だったのは、彼が求めるあの少女が、すでにこの世にはいないということだった。
イゾルデは、やはりプロジェクトの一環として生み出された実験体だった。本人にその自覚はなく、戦闘力もまた皆無だったが、そのベースとなっていたのはアンチK’である。イゾルデはアンチK’の氷をあやつる因子を埋め込まれていた。氷をあやつる――すなわち暴走する炎を抑える因子を育てるためだけに、イゾルデは試験管の中で生まれた。
そしてイゾルデは真相を何ひとつ知らされることもなく、救護班の人間としてネームレスに出会い、惹かれ合った。すべては彼女の中の因子とネームレスとの融和性を高めるためだった。
ネームレスがラボに戻ったあと、イゾルデはその体内で育てていた因子を取り出されて死んだ。
取り出された因子を埋め込まれて完成したのが、ネームレスが装着しているカスタムグローブだった。彼の腕によく馴染むのも当たり前である。なぜならそれは、イゾルデの命を使って生み出されたあらたな命、彼女の分身ともいうべき擬似生命体なのだから。
◎叛意◎
すべてを聞き出したあと、ネームレスは男を見逃し、そして何ごともなかったかのように基地に舞い戻った。
男の告白を頭からすべて信じたわけではないし、かといって全否定しているわけでもない。ただ、ネームレスの中に、拭い去りがたいネスツへの疑惑が生じたことは確かだった。
いわれてみれば、思い当たることはいくつもある。このグローブを装着した時の一体感や安心感は、そこにイゾルデの命が息づいているのだと考えれば妙に納得がいくし、ネームレスがどんなに目覚ましい活躍を見せても上層部がいっこうにあの約束を守ってくれる気配がないのは、すでにイゾルデがいないからなのかもしれない。だがそれを信じることは出来ない。
いずれにしろ、真実を突き止めなければならない。
◎開幕◎
あの日から、ネームレスは自分の周囲を注意深く観察するようになった。工作員として行動するようになって以来、以前のようなきつい監視はつかなくなかったが、それでも何者かの視線を感じるような気がする。やはり自分はネスツの大きなてのひらの上で転がされているモルモットなのかもしれないと思うと、ネームレスは以前にも増して寡黙になり、彼の生み出す炎もまた、鬱積した思いのぶんだけ強くなっていった。
ことの真相を掴めぬまま時はすぎ、人知れず煩悶を続けていたネームレスのもとに、重要な任務が回ってくる。
KOFに参戦し、裏切り者たちを始末せよ――。
ネームレスはここで強気な賭けに出た。
もし今回の任務を無事に成し遂げたのなら、棚上げになっていたあの約束を果たしてもらう。その確約を得られなければ命令違反に問われようとも参戦はしない。一工作員の身でそんな要求を上に突きつけることがどれほど分不相応なことか、ネームレスにもよく判っていたが、これはネスツの反応を見るにはいい機会でもあった。
しかし上層部は、拍子抜けするほどあっさりとネームレスの要求を呑んだ。
ひょっとすると、あの裏切り者のいっていたことはすべてでたらめで、本当はイゾルデもデイモスで元気にしているのではないか――ネームレスの脳裏に、一瞬、そんな考えがよぎったが、そう断定するにはまだ早すぎる。
上層部に自分の意見が通ったことで、ネームレスはKOFに参戦することが決まった。
グローブをいとおしげに磨きながら、ネームレスは思う。
今度の任務を無事にやり遂げたとして――もしネスツがイゾルデと引き合わせてくれるのなら、自分は一生ネスツの飼い犬でかまわない。
だが、もしネスツが何かしらの理由をつけて彼女と会わせてくれるのを拒んだとしたら、万難を排してでも彼女を捜し出し、彼女を連れてネスツから逃げ出そう。
そしてもし、あの裏切り者がいっていた通り、すでにイゾルデがこの世の人ではなく、自分が騙され続けていたのだとしたら、その時は絶対にネスツを滅ぼさずにはおかない。
自分が任務に失敗するということを、ネームレスは微塵も考えなかった。